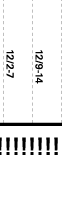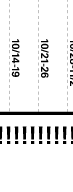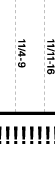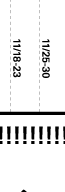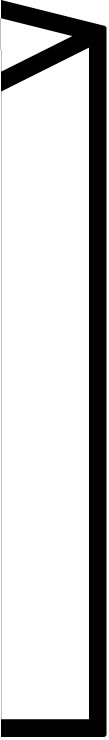

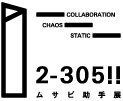
COLLABORATION Vol.3 揺らぎの部屋
やわらかそうなクッションが数個、窓を連想させる立体物が一つ、そして、天井からぶらさがるランプ。「揺らぎの部屋」に入ると、一瞬、誰かの部屋を訪れたような錯覚を覚えてしまう。床一面に白い石が敷き詰められたその空間は初めて訪れる場所であるのに、不思議と居心地が良い。
長谷川冬香の油彩画、『cloth(蜘蛛の巣模様)』、『cloth(魚模様)』、そして『cloth(Geometric pattern)』を鑑賞していると、平面作品でありながらも、モチーフであるクッションの布の表面に自分の指先を滑らせているような感覚に陥る。それは写実的にモチーフが描写されているという事より、画面中の筆跡がしるす、薄く溶かれた油絵の具のなめらかさや、やわらかさが生む「質」に起因しており、距離を置いて再び作品を眺めてみると、そこにはつい先ほどまで人がいたような温度や、湿度さえも感じ取ることができる。シンポジウムにおいてパネリストとして参加した長谷川(冬)は「触覚」を強く意識して制作していると言っていたが、それは作品に使用されている乳白がかった色彩や、繊細な線の集積からも伝わってくるだろう。
シンボリックでモニュメンタルになりがちな彫刻を避け、作品の美を純粋に感じるため、また自らが素材を消化し、その存在の理解を深めるために、長谷川佐知子は石の表面を包み込むように線でおおう工程を施す。その結果、展示室奥に配置されたクリーム色の彫刻作品『wall(beige)』は、縦1500㎜、横360㎜、幅2060㎜とそれなりに大きいものの、観る者に圧迫感を与えていない。波打つ毛並みのようなノミ跡は全体に軽やかさを加えるだけでなく、停止しているはずのライムストーンに生命力までもを与えているようだ。部分的に窓のようだったり、玄関のようだったりと、ユニークな外観を持つものが多い長谷川の作品だが、随所に作家が理想とする用具の組み合わせや形態が詰め込まれているという背景を知ると、小さな単位で作品を隈無く鑑賞するという新たな楽しみ方が生まれる。
長谷川冬香と長谷川佐知子の作品は、互いに調和するように穏やかな空気を紡ぎ出している。しかし、9月25日の山田毅の朗読パフォーマンス『つくりたてのポトフ』を鑑賞すると、それらの展示作品に対して妙な親近感を覚えることとなる。山田が二人の展示作品を題材に三日間で書き上げたという、オリジナリティ溢れる想像の物語に最初鑑賞者はただ耳を傾けるしかないが、時間の経過と共に笑いがおこり、物語に登場した作品を時折眺める者が増え、会場の緊張感がなくなっていくと、この物語の内容における詳細はさほど重要でないことに気付く。アーティストがある種のエンターテイナーであると定義づける事は可能だが、場の関心度が上がり、この朗読を聞くまでは知り得なかった作品に対する面白みをそれらに感じる事ができるという点に関して言えば、今回のパフォーマンスが意味する部分は大きかったのではないだろうか。
「揺らぎの部屋」に展示された長谷川冬香と長谷川佐知子の作品。そして、一日限定で突如加わった山田毅のパフォーマンス。来場者がどのように全体を観たかが非常に気になる、異色の作家が集まった展示であった。
小川萌子(芸術文化学科3年)



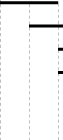






Copyright (C): 2010 Musashino Art University Museum & Library All Rights Reserved.