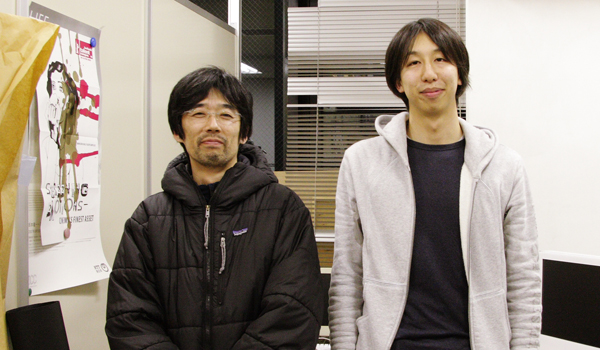
長井勇助手(映像学科研究室)インタビュー
聞き手:宮下晃久氏(写真家、本学非常勤講師)
・一般的には、思い出を記録するための装置として、カメラが作られることが多いと思うんです。例えば、人の顔を自動検出する機能だったり、肌の色がきれいに出るホワイトバランスを自動設定する機能だったり、そういった機能に特化したカメラが、一般消費者向けに売り出されている流れがあると思います。その流れの中で、自分の内を表現する手段として、外を撮るカメラというものを選択しているのはどうしてでしょうか?
長:う—ん。簡単だからじゃないですか。
宮:えっ、本当に?
長:だって、手っ取り早いじゃないですか。
宮:そうなんだ。僕はちがう。
長:う〜ん…。「何で描かないのか?」「何でつくらないのか?」って意味の質問ですよね?
宮:ちがう、ちがう。数あるメディウムの中で、何で写真を選んだんだ?っていう話。
・自分の内の表現をする上でも、外の現実物がなければ成立しないメディウムですが、なぜそれを選択したのでしょうか。
長:矛盾していたら申し訳ないんですが、「写るものを信じていない」という認識で撮っているんですよ。「そのものを撮って(写して)いない」という認識で。
宮:そう思い始めたのは何で?大学在学中の間で、そう思い始めたのはいつ?
長:例えば、同じ対象(被写体)で画角を変えて撮った2枚の写真があるじゃないですか。その差に、僕はあまり意味を感じなかったんですよ。写真を選ぶ中で、感覚的にアングルを変えて撮っただけの写真に差違を見出せない。それは、写真を撮る人としてダメだと思うんですけど…。
宮:あ、あれだ。普通に写真を撮るときは、こう撮って、アングルを変えてこう撮って、近寄って撮って、そこから選ぶでしょ! それに、もう意味を見出していないんでしょ。
長:そうなんですよね。そして、さらにその中から「これはいいね」とか、人によっては「こっちのほうがいいねぇ」とかがあるじゃないですか。もう、それが意味ないなと思ったんですよ。そうすると、もう全然(写真を)選べなくなって。それが、学部3年の終わり頃ですね。
・そこから現在の作風に至るのは、どのような経緯からですか?
長:まっすぐ繋がるかどうか分からないんですけど…。4年になって映像学科の篠原先生のゼミに入ってからですね。写真のゼミではないので、今まで身を置いてきたいわゆる写真(界)の話が通じない環境の中で、自分が今まで撮ってきた写真が何だったのかを考え直す場所でした。指導の中で先生は「何を撮りたいんだ?」「何が好きなんだ?」と問題解決の糸口をみつけようとするんですけど、自分の中から「これが撮りたい」「これが好き」とパッと出てこなくて。
ゼミの面談で、3年次の進級制作展の写真を見せていたときに、1枚の写真を差して「これの魅力がわかるか?」って聞かれたんです。でもそのときは、自分では魅力をわかっていなかったんです。自分でわかっていなくて、良いと思っていなくても、その作品の構成なり構造なりを自分で理解し撮り続けることが、消去法的に自分のやりたいことを確認することになるのかな、と。とりあえず、やってみないと、どちらもわからないじゃないですか、いいのか悪いのかを含めて。だから、やってみて好きじゃないとか好きとかを決める、というところから来ているんですけれどね、これ(卒業制作以降の作品)も。
この写真は、結局は水平と垂直の構成になってくるんですけれど、その構成をシンプルに画面に置く、というか、情報としてのせてゆくイメージですね。この緑が無いと、立体なのか、現実物なのか、模型なのか、何なのかわからないじゃないですか。スケールを示す意味でも、空間がここに存在するのだけれども平面化されている、ということを見る人に気づかせる為の情報として、のせている緑色というか。そうして、情報として写真をとらえて作っているんです。進級制作展で先生が指摘した写真も、そのようなところがありました。今考えると。ゼミの指導の中で、要素とか構成とか構造を確認し、そこから「画をつくる上で、何が必要なのか」をひとつひとつ抽出していき、今の制作スタンスになりました。
・この作品は「写真作品である」というのが魅力のひとつですよね。これが描かれたものであったら、ここまで魅力あるものではなかったと思うんです。
長:そこに助けられているというか、写真の性質をちょっと否定しているような制作スタンスでありながら、写っている対象が現実の事物であるという共通認識で、作品が成り立っている、強度をもっているということですよね。それは、写真作品だからこそ可能なんですよね。
interviewer
高橋奈保子(視覚伝達デザイン学科研究室助手)
黒澤誠人(美術資料図書館)
